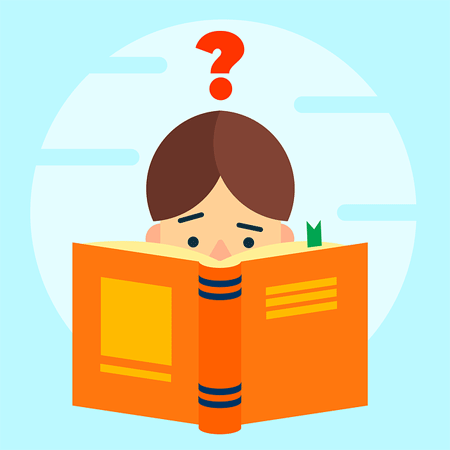
様々な文学作品を読んだり音楽を聴いたりしていると新約聖書に関連した内容がよく出てくるので、新約聖書を読んでおきたくなります。
ただし新約聖書は一般的な単行本5冊分前後くらいの分量はあるのでいったい何日で読み終わるか気になります。
ここでは新約聖書を読み終えるのに必要な日数の目安を紹介します。
新約聖書
私も大して詳しくありませんが、イスラエル民族の神話や歴史や預言の書のような文書を集めた文書群があり、ヘブライ語聖書と呼ばれたりしており、キリスト教徒は旧約聖書と呼んだりしています。
本で読んだ内容によれば、ヘブライ語聖書はユダヤ教関連の文書群で、ユダヤ教の社会で生きていたナザレ村で大工をしていた職人のイエスがその当時のユダヤ教の在り方を批判したり、イエスなりに神の無条件の赦しなどを人に伝えたりし、イエスの弟子になる人も出て来て、エルサレムの神殿に行って宗教的政治的に権威のある人間を批判したりし、そのようなことをしたため最終的に処刑され、イエスの弟子たちが弟子たちなりにイエスの死の意味を考えたりしてキリスト教ができてきたらしいです。
イエスの死後、弟子たちが必要があって各地の信徒の組織に送った複数の手紙や、イエスの言動などをまとめた文書や、政治的な事情か何かの事情があって書かれた黙示録などをまとめた文書群が新約聖書らしいです。
ヘブライ語聖書はユダヤ教関連の文書群で、この文書群の中に神がアブラハムと契約を結ぶ話などが出てきて、ユダヤ教もイスラム教もキリスト教もアブラハムと契約を結んだ神を信仰している宗教で、岩波文庫のコーランを読んだところコーランに新約聖書の福音書と同じような内容が出て来て、イエスの誕生の話が載っていたりします。
日本に住んでいると、作家であれ、自分が通っていた大学の先生であれ、周囲にキリスト教徒が結構いるのでキリスト教に関する知識は入ってきやすいです。
日本聖書協会や、カトリック教会の出版社や、岩波書店などの一般的な出版社から新約聖書は多数出版されています。
参考
色々なものに新約聖書がらみのものがよく出てくる
トルストイや三浦綾子などキリスト教徒の作家ならその作品にはキリスト教関連の内容が多数出てきます。
メタルバンドのインペリテリのアルバム「Answer to the Master」や「Eye of the Hurricane」などに収録されている曲に聖書からの引用が多数出て来て、キリスト教の聖書を読んだことがないと歌詞の意味が分からなかったり、歌詞カードの日本語訳はキリスト教の聖書を読んだことがない人が訳しているらしくおかしな訳になっていたりします。
ANSWER TO THE MASTER – Impellitteri
新約聖書は現代人の感覚で見て良いことがたくさん書いてある文書群というわけではない
新約聖書はキリスト教で正典とされている文書群なので、宗教の教典なら何かためになる良いことが書いてあると思う人もいるかもしれませんが、現代人の感覚から見て単純に良いことばかり書いてあるわけではありません。
書いた人々の宗教観が分かる文書の数々が載っています。
イエスが語っている神の無条件の赦しなどは現代人も共感できます。
一方、新約聖書は2000年近く前の奴隷制社会で生きていた人々が書いた文書なので、弟子たちの手紙などを読む限り現代人が持っている人権意識や多様性を認め合う寛容な精神は欠けています。
全体を通じて首尾一貫した内容というわけではない
新約聖書は様々な人が様々な事情で書いた文書を集めたものなので、全体を通じて完全に首尾一貫した内容になっているわけではありません。
書いた人が異なれば宗教観も違いがあります。
新約聖書は3ヶ月以内で読めるかもしれない
日本聖書協会の新共同訳聖書という日本語訳の聖書の「新約聖書」の部分を読みました。
私は人並みはずれて本を読むのが遅い方ですが、列車で移動中に列車内で読んだり、列車の待ち時間に駅で読んだりするスタイルで、約3ヶ月間で読み終わりました。
たいていの人は私より読むのが速いので、おそらく3ヶ月以内に読み終わります。
新約聖書の例
新約聖書だけの聖書ならある程度薄い聖書が何種類もあります。
くまざわ書店なり紀伊國屋書店なりジュンク堂なり喜久屋書店なり三省堂書店なりコーチャンフォーなり大きめの書店に行けばいくらでも売られています。ブックオフなど大きめの古本屋でもよく見かけます。
“原典に忠実な翻訳と周到な注釈によって、新たな読解の可能性を開いた「岩波版新約聖書」。新約聖書学の達成を踏まえた訳語の大胆な工夫と、聖書特有の表現や翻訳上の考え方を詳説する傍注、巻末の用語解説によって、新約の世界を立体的に甦らせる。その特長を一層深めた、全一冊合本版の刊行から一九年を経ての初の改訂。”
「新共同訳」は日本で読まれている日本語訳聖書の中でかなりメジャーな聖書。
参考書籍
“「聖書」とは「聖なる書物」のことである。それは一冊の書物のように思われていることもあるが、キリスト教の聖書は二つの書物群からなる。「旧約聖書」と「新約聖書」と呼ばれているものである。一度ある書物(群)が「聖書」とされると、それは絶対化される。「聖書」は「神の言葉」であるから絶対だ、と。そして「聖書」の教えに反するとされた者は断罪され、抹殺されるということが起こる。それは「聖書」の権威を傘に、自らを絶対化・正当化する暴力である。”
“イエスの事蹟を人々が書き記し、編纂してきた聖書は、“聖典”として絶対視するものではない。歴史的・批判的立場から聖書と向きあうことこそ、信仰者にも無信仰者にも望まれる。福音書の新しい読み方。”
“特定の教派によらず,自主独立で読む.聖書学者が,自身の経験と思索をもとに提案する「わかる読み方」.”






