
苫小牧東港フェリーターミナルへ公共交通機関で行く方法をみてみます。
※当ブログ運営者が自分用に調べたものです。正確な情報は交通機関の公式情報をご覧ください。
苫小牧東港(周文埠頭)フェリーターミナル
苫小牧東港(周文埠頭)フェリーターミナルは厚真町にあるフェリーターミナルです。
苫小牧東港-敦賀間、苫小牧東港-敦賀間(秋田、新潟経由)の新日本海フェリーが発着しています。
八戸行きのシルバーフェリー、仙台・名古屋行きの太平洋フェリー、大洗行きの商船三井さんふらわあのフェリーが発着している苫小牧西港は苫小牧市内にあり、苫小牧東港とは場所が別ですので注意が必要です。
参考リンク

南千歳駅-苫小牧東港をバスで移動
新日本海フェリーのウェブサイトによれば、JR南千歳駅-苫小牧東港フェリーターミナル間の連絡バスがあります。道南バスが運行しているようです。
確かに先日南千歳駅の前を歩いていたらフェリーターミナル行きの道南バスが停まっていて、旅行客の人たちが乗車していました。
この連絡バスを利用する場合は新日本海フェリーに連絡が必要なようです。新日本海フェリーのウェブサイトの苫小牧東港のページに以下のように書いてありました。(2025/9/12時点)
インターネット予約をご利用で、連絡バスご乗車予定のお客様は、
乗船の前日までにこちらのフォーム>>より連絡バス利用申込をお願いいたします。
バス時刻表
NAVITIMEのサイトに南千歳駅-苫小牧東港フェリーターミナル間の道南バスの連絡バスの時刻表が一応ありました。
ただし、このバスは上記の通り普通の路線バスではなくフェリーの乗船客専用のような雰囲気で、必ずフェリー会社に電話して確認する必要があるようです。
参考リンク
- 苫小牧東港から南千歳 バス時刻表(航路連絡バス:南千歳-苫小牧東港[新日本海フェリー]) – NAVITIME
- 南千歳から苫小牧東港 バス時刻表(航路連絡バス:南千歳-苫小牧東港[新日本海フェリー]) – NAVITIME
JR浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルへ行ける
苫小牧東港フェリーターミナルへJRで行くこともできます。
JR浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまで徒歩で行けます。
冬や夜間の徒歩移動について
私は春の日中にJR浜厚真駅から苫小牧東港まで徒歩で往復したことがありますが、冬も歩ける状態かどうかは分かりません。
北海道では冬の間は徒歩での移動が困難な場所がよくあるので、浜厚真駅と苫小牧東港の間も冬は徒歩での移動が困難な可能性があります。
また夜間に関しては、夜に列車の窓から見た限りでは浜厚真駅周辺と厚真川の橋とフェリーターミナル周辺などは外灯がありますが、それ以外の道路は照明がほとんどないように見え、暗い時間に発着するフェリーを利用する場合に浜厚真駅と東港の間を歩くのは難しいかもしれません。
参考
夜の浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまでの道をJR列車から見た様子
苫小牧-浜厚真間のJR列車
苫小牧駅から浜厚真駅まで普通列車で20分ちょっとで行けます。
列車本数はだいたい2〜3時間に1本程度です。
浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまで1.6kmほどなので、徒歩で30分もかからずに行けます。
参考リンク
苫小牧駅から浜厚真駅までの様子
苫小牧駅から勇払駅までの様子
勇払駅から浜厚真駅までの様子
日高本線の列車は少なく、なおかつ鵡川から先は廃線になってしまった
浜厚真駅がある日高本線の列車は本数が少ないです。
また、日高本線の鵡川から先は廃線になってしまったり、他のJR路線など多くの場所で列車本数が減らされ続けたりして不便な状況です。
一生に一度は乗ってみたい豪華列車より、一生乗れる普通列車をきんちと運行してほしいと以前誰かが言っていました。
日本で生まれ育っていると、日高本線は災害で線路が壊れ復旧に多くの金がかかるが利用者は少なく赤字なので廃線は止むを得ない、その他の路線も赤字なら廃線は止むを得ない、という考え方に陥ってしまう場合が多いですが、世界ではあまり一般的で無い考え方です。
以下は、世界では持続可能な社会を作るため環境負荷の低い鉄道が今まで以上に重要になっている現在、なぜ時代に逆行してこれほど日本の鉄道網が崩壊してきているかについての参考記事です。

上記リンク先の記事に以下のようなことが書いてありました。
地脇聖孝「ローカル鉄道に国・自治体・住民はどう向き合うべきか」からの引用

上記リンク先の記事に以下のようなことが書いてありました。
このような交通政策は間違っています。同じ交通施設でも道路や港湾、空港は公共事業として公的資金で建設がなされ維持されています。その施設を自家用車やバス、トラック、船舶、航空機などが利用していますが、建設費は負担していません。しかし、鉄道の場合は施設と運行車両が一体として運営されています(太字引用者)。とくにJR北の場合、長大路線と積雪寒冷という本州にはない悪条件を抱えての運営で、赤字がかさむのは当然です。
鉄道は通学・通院・買い物・ビジネス活動・貨物輸送・観光など、日々の暮らしや仕事に直結しています。とくに北海道にとっては、日本の食料基地としての農水産物の輸送、国際的に人気が急拡大しているインバウンドにとって不可欠な移動手段です。さらに、北海道の鉄道は、明治期以降、石炭輸送を皮切りに、内陸部開拓に重要な役割を果たしてきました。そのことが持つ歴史的・文化的価値も重要で、これからの地域発展を考える上ではかけがえのない財産となります。
小田清「JR北海道の路線廃止と地域対応 ―鉄路は地域発展に不可欠―」からの引用
参考リンク

浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまでの道の周辺の様子

浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまでの道の周辺1

浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまでの道の周辺2 JR日高本線の橋

浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまでの道の周辺3 JR日高本線の橋

浜厚真駅から苫小牧東港フェリーターミナルまでの道の周辺4
ヒグマに注意
苫小牧東港フェリーターミナルの周辺にもヒグマがおおぜい暮らしているので、ゴミを捨ててヒグマをおびき寄せたりしないよう注意しましょう。
ヒグマたちと共存する方法は以下の本などに書いてあります。
“行動から人身事故事例まで半世紀の研究成果を集大成
あらゆる動物の行動には必ず目的と理由がある。ヒグマの生態を正しく知るには、ヒグマに関するあらゆる事象、生活状態を繰り返し検証することである。ヒグマの実像を知ることができれば、人間とヒグマのトラブルを避ける方策も見出せるし、ヒグマを極力殺さず共存していけると考えられる--”
“ヒグマの居る山野ではホイッスルと鉈が必需品です
市街地、放牧地、農地等への出没防止には有刺鉄線柵や電気柵を張る事です”
船の脱炭素化をどうするかについて
日本はまもなく炭素予算を使い切ろうとしており危機的な状況にある中、船と飛行機は今のところ化石燃料で動いていて、脱炭素をどのように進めるか気になります。
日本が今のペースで温室効果ガスの排出量を減らした場合、減らすペースが遅すぎて温室効果ガスの排出量を実質0を達成したときにはすでに炭素予算を使い切ってさらに排出してしまい1.5度以上の気温上昇が起きてしまうと本などで読みました。
参考書籍
“環境・エネルギー分野の第一線で活躍する執筆陣が、地球温暖化の現状・対策から再生可能エネルギー、カーボンニュートラルによる地域活性化まで、115の主要テーマを図入りでコンパクトに解説。気候危機の現状から地域活性化まで激動する世界の「脱炭素」の今がわかる!隔年刊行。”
“今の日本の気候政策では、将来に大きな禍根を残すことになる。40人を超える専門家による、気候変動・エネルギー政策の課題と提言。”
参考リンク
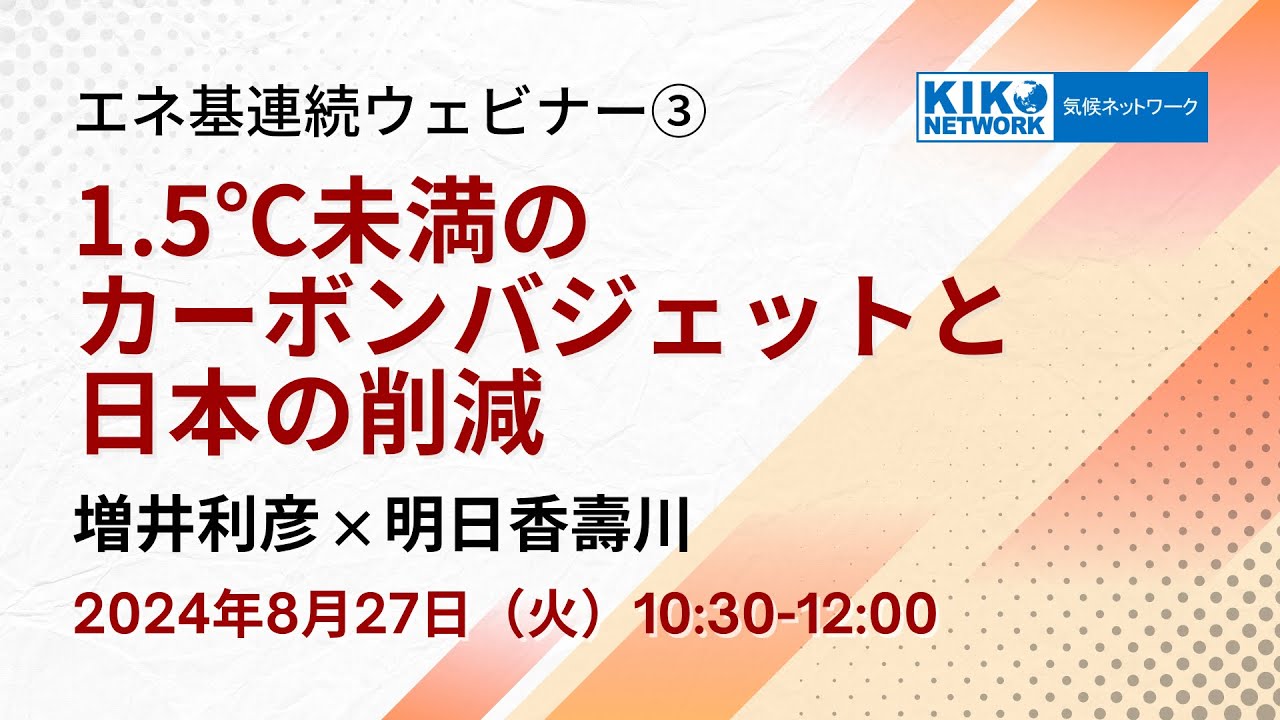
一般社団法人共生エネルギー社会実装研究所 編著「最新図説 脱炭素の論点 2023-2024」旬報社 を読んだところ、船と飛行機などの脱炭素化にはまだ時間がかかり、一方で発電や、自動車などすでに電化できる技術があるものは再生可能エネルギーで発電してその電気で動かすことで脱炭素化が可能で、交通関係の温室効果ガスの排出量の割合としては自動車からの排出が圧倒的に多く飛行機・船の割合は非常に小さいため、とりあえず発電や自動車の電化やその他技術的にすでに脱炭素化する算段ができているものの脱炭素化を早く進めて温室効果ガスの排出を減らせるだけ減らしておいて、その後の飛行機・船、製鉄などの脱炭素化に時間がかかる分野の脱炭素を進めるための時間を確保する、という段取りで進めるしかないというようなことが書いてありました。
詳しくは「最新図説 脱炭素の論点」などをご覧ください。「最新図説 脱炭素の論点」は全体の要点を説明している本ですが、参考文献が多数載っているので参考文献を読むことでさらに詳細も分かります。
地球上の自然の循環のスピードの範囲内でしか人間は活動できないため、再生可能エネルギーに変えさえすれば済むわけではなく、エネルギーを使う量を減らしたりクルマの総量を減らしたり鉄道のような使うエネルギーの少ない交通機関を使うようにしたりしなければ人類は続かないというような説明が以下の本などにありました。
“人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機の時代。気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るだろう。それを阻止するためには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのか。いや、危機の解決策はある。ヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていた。世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす。”
参考

“サケを獲る権利、
川を利用する権利、
私たちの先祖が当然のように持っていた
権利を取り戻したい…
(ラポロアイヌネイション 差間正樹)”
“──先住権について学ぶことは 日本人としての立ち位置を理解すること
近代とともに明治政府は蝦夷島を北海道と名称変更して大量の和人を送り込みました。支配を確立した政府はそれまでアイヌが自由に行ってきたサケの捕獲を一方的に禁止し、サケを奪われたアイヌは塗炭の苦しみを経験しなければなりませんでした。ラポロアイヌネイションは、近代日本の植民地政策によって奪われた浦幌十勝川河口でのサケの捕獲権を、先住権の行使として回復したいと主張して裁判を始めたのです。
アイヌの自覚的な先住権を求めるたたかいはこうして始まりました。北海道が明治政府の支配による入植植民地であり、アイヌの人々への抑圧と収奪によって成り立ってきたことを、植民者である和人はなかなか自覚できないできました。アイヌ先住権を学び、応援することで、和人は自分たちの立ち位置をようやく理解する入口に差し掛かったのです。
[刊行にあたって──北大開示文書研究会 共同代表 殿平善彦]”
“国鉄「分割・民営化」の破綻を総括 鉄道の復権による地域社会の再生を考える!
北海道の鉄路は全路線の半分に当たる10路線が維持困難として廃線の危機に直面している。国鉄の「分割・民営化」から30年、JR各社では不採算路線の廃止などで、全国的な鉄道網の分断が進行している。鉄道は安全性、定時性、高速性で高く評価され、地域社会の発展に不可欠であるのに、政府の自動車・航空偏重政策の前に危機を迎えている。
本書は、JR北海道の危機的状況にたいして、新自由主義による従来の「分割・民営化」路線の破綻を総括し、「持続可能な社会」の考え方を基本に、鉄道路線の存続・再生、地域経済・社会の再生の道を提起する。”
北海道に入植した和人の歴史が短いため「北海道の歴史は短い」という言い方をたまに耳にしますが、北海道には数万年前から人が住んでおり、北海道の歴史は長いです。
“北の地から日本の歴史を見つめ直す視点で、専門家6人がまとめた北海道史の概説書。高校生以上の読者が理解できるように内容を精選した。2006年刊行の下巻に次ぐ労作。上巻ではアイヌ民族に関する詳述を含め、旧石器時代から箱館開港までを解説した。”





![イチからわかるアイヌ先住権 アメリカ・北欧・オーストラリア・台湾の歴史と先進的な取り組みに学ぶ (ラポロアイヌネイション&北大開示文書研究会オンライン学習会[講演集])](https://m.media-amazon.com/images/I/51jaa+ex6PL._SL160_.jpg)

