
室蘭市の母恋富士への交通案内、アクセス方法の例です。
母恋富士は市街地にある標高156mの低い山で、気軽に登れて山頂からの眺めも良いです。
まず室蘭のJR母恋駅に行く
室蘭市外にいる場合はとりあえずJRなどで室蘭に行き、JR母恋駅まで行きます。
札幌から室蘭にJRで行く場合
JR札幌駅から室蘭駅に行く場合の例です。
札幌から室蘭までの「Sきっぷ」は無くなってしまった
以前は札幌から東室蘭まで特急の自由席で往復できるSきっぷを使って「北斗」でも「すずらん」でも何でも都合の良い時刻の特急に乗って行けましたが、札幌-東室蘭のSきっぷが廃止になってしまい、めっきり不便になりました。
「乗車券往復割引きっぷ(札幌-東室蘭〜室蘭)」+「すずらんオプション特急券」も無くなってしまった
札幌-東室蘭のSきっぷが無くなった後は乗車券往復割引きっぷ(札幌-東室蘭〜室蘭)とすずらんオプション特急券というきっぷが発売され、Sきっぷよりは値段は高いですがこのきっぷで特急「すずらん」の自由席で札幌-東室蘭を往復できました。しかしこれも廃止になってしまい、めっきり不便になりました。
「特急トクだ値1」「特急トクだ値14」くらいしか無くなってしまった
現在では札幌-室蘭の特急「すずらん」は全席指定になってしまい、私がJR北海道の公式情報を調べた限りでは札幌-室蘭の特急の割引切符は「えきねっと」で前日までか14日前までに購入しなければならない「特急トクだ値1」「特急トクだ値14」くらいしかなくなってしまったようです。
「Sきっぷ」や「乗車券往復割引きっぷ(札幌-東室蘭〜室蘭)」は出発する当日に「今日は室蘭に行くか・・・」と決めて切符を買って気軽に乗れましたが、「特急トクだ値○○」は乗車日より前に購入しておかなければならないきっぷなので、忙しいビジネスパーソンたちが休日にちょっと外出するようなケースでは使いにくく非常に不便です。
「特急すずらん」が全席指定になって以降は私は全く「特急すずらん」に乗れなくなってしまいました。
特急「すずらん」が全席指定になってめっきり乗りにくくなって乗客数が減って、数年後には乗客が少ないという理由で特急「すずらん」が廃止になる、というような末路にならないか不安です。
「一日散歩きっぷ」の発売期間なら普通列車で往復できる
特定の範囲の普通列車の自由席乗り放題の「一日散歩きっぷ」の発売期間なら「一日散歩きっぷ」を使って普通列車で札幌-室蘭を往復できます。
ただし、「一日散歩きっぷ」は土日祝などにしか発売されず、最近の「一日散歩きっぷ」は発売期間と利用期間が限られており、春から秋までくらいしか発売されない年が多いです。
「一日散歩きっぷ(2025年度設定)」の利用期間は「2025年4月19日~2025年11月9日までの土曜・休日」とJR北海道の公式サイトに書いてありました。
2025年11月9日を過ぎて「一日散歩きっぷ(2025年度設定)」が終了した今では私は札幌から室蘭まで列車で行くことができなくなってしまいました。
参考リンク
北海道内の鉄道は廃線や減便や便利な切符の廃止が続いて危機的な状態になっています。道路や空港に莫大な税金が注ぎ込まれることに異議を唱える人は少ない一方、鉄道は赤字路線なら廃線は仕方ないと考える人が多いです。
鉄道を採算だけで評価する日本独特の考え方に陥らず、地域の社会資本として評価する世界標準の考え方を学びましょう。
参考リンク



参考書籍
“国鉄「分割・民営化」の破綻を総括 鉄道の復権による地域社会の再生を考える!
北海道の鉄路は全路線の半分に当たる10路線が維持困難として廃線の危機に直面している。国鉄の「分割・民営化」から30年、JR各社では不採算路線の廃止などで、全国的な鉄道網の分断が進行している。鉄道は安全性、定時性、高速性で高く評価され、地域社会の発展に不可欠であるのに、政府の自動車・航空偏重政策の前に危機を迎えている。
本書は、JR北海道の危機的状況にたいして、新自由主義による従来の「分割・民営化」路線の破綻を総括し、「持続可能な社会」の考え方を基本に、鉄道路線の存続・再生、地域経済・社会の再生の道を提起する。”
“国土交通省のローカル鉄道の見直しの提言を批判する! これでは国の骨格が崩れる!
第1部 ローカル鉄道問題はローカルだけの問題ではない(検討会設置の契機と背景/検討会と提言の枠組み・概要/論点/あるべき方向)/第2部 提言に対するQ&A(ローカル線を取り巻く現状に関するQ&A/ローカル鉄道の廃止と地域公共交通の利便性に関するQ&A/地方自治体の責任と役割に関するQ&A/国の責任と役割に関するQ&A/地域社会における鉄道の役割に関するQ&A)/第3部 地域のための鉄道を求めて(鉄道は「社会的生産過程の一般的条件」/JR北海道のもっている矛盾と二つの解決の道/第一の道における理論的な枠組みー「生産者と消費者」の欺瞞性/第二の道をもとめてー鉄道の再生の展望)”
JR母恋駅から母恋富士登山道入り口まで徒歩で行く
母恋富士の登山道入り口は複数あります。
以下はJR母恋駅から比較的近い登山道入り口までの行き方の例です。
母恋富士登山道入り口まではJR母恋駅から徒歩で行けます。
距離は約550mです。
母恋富士下のサクラ並木を通って進みます。

母恋富士下サクラ並木
サクラ並木のエリアを過ぎて道なりに左に曲がって少し進むと母恋富士の登山道の入り口があります。

母恋富士下の桜並木の道を進んだ先にある母恋富士の登山道入り口
母恋富士は住宅地の中にある低い山です。
登山道が整備されており、低い山なので簡単に登れますが山頂からの眺めは良いです。

母恋富士の登山道

母恋富士山頂
白鳥大橋も見えます。

母恋富士からの眺め 湾と白鳥大橋の方
測量山も見えます。

母恋富士からの眺め 測量山の方
製鋼所や製鉄所も見えます。

製鋼所や製鉄所の方
登山道の途中にちょっとした広場や東屋もあります。

東屋で一休み

ちょっとした展望所
登山道の入り口は複数あり、登山道はいくつかに分岐します。

登山道の分岐の看板
製鉄などの脱炭素化をどうするかについて
室蘭には製鉄所があり、汐見公園の展望台などから製鉄所を眺めていると煙突のようなところから炎が噴き出る様子などを見ることができます。
自動車などの交通の脱炭素も進んでいませんが、製鉄などの脱炭素も難易度が高そうでどのように脱炭素を進めるか気になります。
日本が今のペースで温室効果ガスの排出量を減らした場合、減らすペースが遅すぎて温室効果ガスの排出量を実質0を達成したときにはすでに炭素予算を使い切ってさらに排出してしまい1.5度以上の気温上昇が起きてしまうと本などで読みました。
参考書籍
“環境・エネルギー分野の第一線で活躍する執筆陣が、地球温暖化の現状・対策から再生可能エネルギー、カーボンニュートラルによる地域活性化まで、115の主要テーマを図入りでコンパクトに解説。気候危機の現状から地域活性化まで激動する世界の「脱炭素」の今がわかる!隔年刊行。”
“今の日本の気候政策では、将来に大きな禍根を残すことになる。40人を超える専門家による、気候変動・エネルギー政策の課題と提言。”
参考リンク
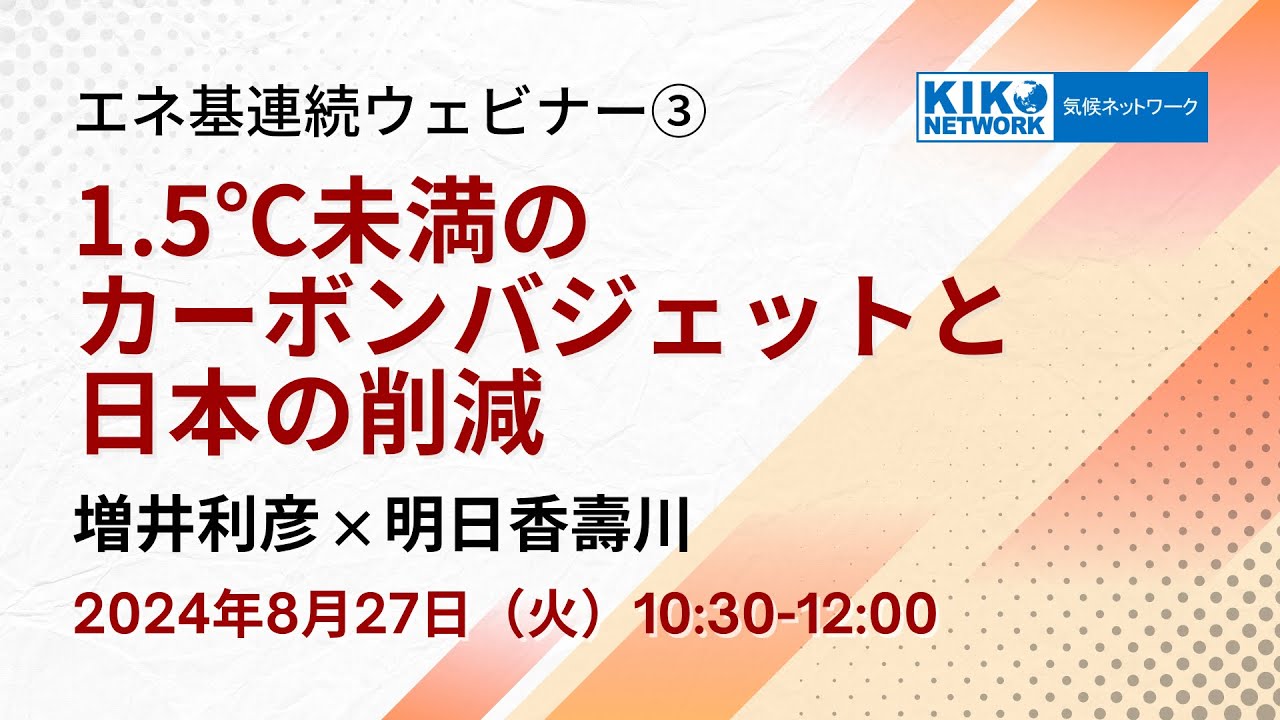
一般社団法人共生エネルギー社会実装研究所 編著「最新図説 脱炭素の論点 2023-2024」旬報社 を読んだところ、とりあえず早く発電を100%再エネにして、自動車の電化やその他技術的にすでに脱炭素化する算段ができているものの脱炭素化を早く進めて温室効果ガスの排出を減らせるだけ減らしておいて、その後の飛行機・船、製鉄などの脱炭素化に時間がかかる分野の脱炭素を進めるための時間を確保する、という段取りで進めるしかないというようなことが書いてありました。
詳しくは「最新図説 脱炭素の論点」などをご覧ください。「最新図説 脱炭素の論点」は全体の要点を説明している本ですが、参考文献が多数載っているので参考文献を読むことでさらに詳細も分かります。
地球上の自然の循環のスピードの範囲内でしか人間は活動できないため、再生可能エネルギーに変えさえすれば済むわけではなく、エネルギーを使う量を減らしたりクルマの総量を減らしたり鉄道のような使うエネルギーの少ない交通機関を使うようにしたりしなければ人類は続かないというような説明が以下の本などにありました。
“人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機の時代。気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るだろう。それを阻止するためには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのか。いや、危機の解決策はある。ヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていた。世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだす。”
室蘭市の母恋富士への交通案内、アクセス方法の例でした。
北海道の情報
“サケを獲る権利、
川を利用する権利、
私たちの先祖が当然のように持っていた
権利を取り戻したい…
(ラポロアイヌネイション 差間正樹)”
“──先住権について学ぶことは 日本人としての立ち位置を理解すること
近代とともに明治政府は蝦夷島を北海道と名称変更して大量の和人を送り込みました。支配を確立した政府はそれまでアイヌが自由に行ってきたサケの捕獲を一方的に禁止し、サケを奪われたアイヌは塗炭の苦しみを経験しなければなりませんでした。ラポロアイヌネイションは、近代日本の植民地政策によって奪われた浦幌十勝川河口でのサケの捕獲権を、先住権の行使として回復したいと主張して裁判を始めたのです。
アイヌの自覚的な先住権を求めるたたかいはこうして始まりました。北海道が明治政府の支配による入植植民地であり、アイヌの人々への抑圧と収奪によって成り立ってきたことを、植民者である和人はなかなか自覚できないできました。アイヌ先住権を学び、応援することで、和人は自分たちの立ち位置をようやく理解する入口に差し掛かったのです。
[刊行にあたって──北大開示文書研究会 共同代表 殿平善彦]”
北海道に入植した和人の歴史が短いため「北海道の歴史は短い」という言い方をたまに耳にしますが、北海道には数万年前から人が住んでおり、北海道の歴史は長いです。
“北の地から日本の歴史を見つめ直す視点で、専門家6人がまとめた北海道史の概説書。高校生以上の読者が理解できるように内容を精選した。2006年刊行の下巻に次ぐ労作。上巻ではアイヌ民族に関する詳述を含め、旧石器時代から箱館開港までを解説した。”
“行動から人身事故事例まで半世紀の研究成果を集大成
あらゆる動物の行動には必ず目的と理由がある。ヒグマの生態を正しく知るには、ヒグマに関するあらゆる事象、生活状態を繰り返し検証することである。ヒグマの実像を知ることができれば、人間とヒグマのトラブルを避ける方策も見出せるし、ヒグマを極力殺さず共存していけると考えられる--”





![イチからわかるアイヌ先住権 アメリカ・北欧・オーストラリア・台湾の歴史と先進的な取り組みに学ぶ (ラポロアイヌネイション&北大開示文書研究会オンライン学習会[講演集])](https://m.media-amazon.com/images/I/51jaa+ex6PL._SL160_.jpg)

