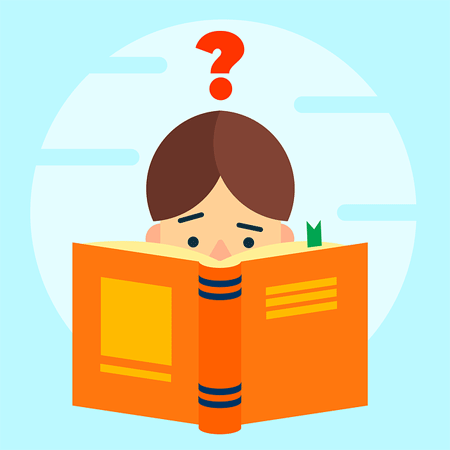
様々な文学作品を読んだりしているとヘブライ語聖書(キリスト教徒が言う旧約聖書)に関連した内容がよく出てくるので、ヘブライ語聖書を読んでおきたくなります。
ただしヘブライ語聖書は一般的な国語辞典くらい厚いのでいったい何日で読み終わるか気になります。
ここではヘブライ語聖書を読み終えるのに必要な日数の目安を紹介します。
ヘブライ語聖書
私も大して詳しくありませんが、イスラエル民族の神話や歴史や預言の書のような文書を集めた文書群があり、「ヘブライ語聖書」と呼ばれたりしており、キリスト教徒は旧約聖書と呼んだりしています。
旧約というのはあくまでキリスト教徒の立場による呼び方なので、キリスト教徒の中にも最近は旧約聖書という呼び方を避けてヘブライ語聖書と言ったりする人もいるらしいです。上村静著「旧約聖書と新約聖書 《シリーズ 神学への船出》 第2巻」にそのような説明が書いてありました。
ヘブライ語聖書はユダヤ教関連の文書群で、この文書群の中に神がアブラハムと契約を結ぶ話などが出てきて、ユダヤ教もイスラム教もキリスト教もアブラハムと契約を結んだ神を信仰している宗教ですが、ユダヤ教やイスラム教とヘブライ語聖書の関わりは私は詳しく知りません。
日本に住んでいると周囲にキリスト教徒は結構多く、作家であれ、自分が通っていた大学の先生であれ、キリスト教徒が結構いるのでキリスト教に関する知識は入ってきやすいです。
キリスト教ではヘブライ語聖書と新約聖書が正典で、一般的には信徒たちが聖書を読んでいます。
本を読むのが苦手なキリスト教徒なら礼拝のときに少し読む程度で自分では聖書をめったに読まないという人や、新約聖書は多少読んでいるがヘブライ語聖書はほとんど読んでいない人もいるかもしれませんが、本をよく読むタイプのキリスト教徒はヘブライ語聖書と新約聖書をよく読んでいます。
主にキリスト教徒が運営していると思われる日本聖書協会や、カトリック教会の出版社と思われる出版社や、岩波書店など一般的な出版社からヘブライ語聖書も多数出版され、くまざわ書店なり紀伊國屋書店なりジュンク堂なり喜久屋書店なり三省堂書店なりコーチャンフォーなり大きめの書店に行けばいくらでも売られています。ブックオフなど大きめの古本屋でもよく見かけます。
色々なものにヘブライ語聖書がらみのものがよく出てくる
子どもの頃に観て今もよくテレビで放送される「天空の城ラピュタ」などにヘブライ語聖書が元ネタの乗り物の名前などがよく出てきます。
何か理由があってそうしたのか、何もないところから名前を考えるのが大変だから聖書から採用したのか、理由は知りません。
トルストイや三浦綾子などキリスト教徒の作家ならその作品にはキリスト教関連の内容が多数出てきて、キング牧師も牧師なのでキング牧師の演説にもヘブライ語聖書関連の内容が多数出てきたりします。
テレビでスタジオジブリの映画が頻繁に放送されます。
あまりにもスタジオジブリの映画の放送頻度が高すぎるので、たまには劇場版「銀河鉄道999」か「さよなら銀河鉄道999-アンドロメダ終着駅-」か「1000年女王」か「ユニコ 魔法の島へ」か「迷宮物語」などのアニメ作品を放送してほしいです。
ヘブライ語聖書は現代人の感覚で見て良いことがたくさん書いてある文書群というわけではない
ヘブライ語聖書はキリスト教などで正典とされている文書群なので、宗教の教典なら何かためになる良いことが書いてあると思う人もいるかもしれませんが、現代人の感覚から見てそれほど良いことは書いてありません。
古代の人々の宗教観を表現した文書の数々が載っています。
例えば“敵は抹殺して当然”というような感じの内容や、動物達を殺して燃やして神へ献げる儀式など、現代社会では受け入れられない非倫理的なことがたくさん書いてあります。
倫理観が高まり、国際的に戦争も違法化されている現代では敵であろうと味方であろうと人の命を奪いません。共に生きます。そして予算も人も確保して教育や外交などに力を入れて犯罪や戦争で人の命が奪われない社会を作る努力をします。
国籍が同じでも別でも宗教観が同じでも別でも同じ民族でも別の民族でも近くへ引っ越してきた人とは協力して共に生きます。
動物達に家畜として働いてもらうにせよ動物達の尊厳が守られて暮らせるように動物福祉などに配慮して飼います。
ヘブライ語聖書は7ヶ月以内で読めるかもしれない
日本聖書協会の新共同訳聖書という日本語訳の聖書の「旧約聖書」の部分を読みました。
私は人並みはずれて本を読むのが遅い方ですが、列車で移動中に列車内で読んだり、列車の待ち時間に駅で読んだりするスタイルで、約7ヶ月間で読み終わりました。
たいていの人は私より読むのが速いので、おそらく7ヶ月以内に読み終わります。
速読は無理
速読術を身に付けた子どもたちが本を1ページ目から最終ページまでペラペラめくる動作を繰り返して速読をしているのをテレビで紹介したりしますが、ヘブライ語聖書をあのような速読で読むのはおそらく無理です。
現代の聖書はたいてい国語辞典のような薄い紙に印刷されているので、ペラペラ高速でめくることはできません。
聖書の例
「旧約聖書」はそれなりに分量がおおいので、国語辞典と同じような紙に印刷しても厚さがおそらく5cm前後くらいになってしまいます。
これでは厚過ぎて、持ち歩いて列車内などで読むには不便です。
電子書籍の聖書なら持ち歩いて読めます。
ただし通信機能のあるデバイスで読む場合は公共交通の車内の優先席付近では機内モードなど電波を発信しないモードにしましょう。
紙の聖書でも以下のような持ち歩けるくらいの厚さの聖書もあります。
▲普通の単行本より少し厚い程度の厚さなので持ち歩けますが、とてつもなく薄い用紙を使用しており、普通にページをめくるのも大変なくらいで、普通にめくろうとすると紙がくしゃくしゃになったり折れたりし、場合によっては何もしていないのに気付くと紙が折れていたりします。かなり慎重にページをめくる必要があります。
紙が薄過ぎて日本国内で印刷できないからなのかどうか分かりませんが、主に聖書を印刷していて極薄紙の印刷をする技術を持っているオランダの印刷所で印刷したらしいです。
▲岩波文庫の旧約聖書があります。文書ごとに分かれているのでそれぞれに探して買うのが大変です。
▲岩波書店の旧約聖書翻訳委員会訳は文書ごとに分かれているので持ち歩けますが、価格が高いです。
日本国内のキリスト教徒などがよく使っている一般的な聖書は分厚いです。厚さが5cm以上あります。
参考書籍
“「聖書」とは「聖なる書物」のことである。それは一冊の書物のように思われていることもあるが、キリスト教の聖書は二つの書物群からなる。「旧約聖書」と「新約聖書」と呼ばれているものである。一度ある書物(群)が「聖書」とされると、それは絶対化される。「聖書」は「神の言葉」であるから絶対だ、と。そして「聖書」の教えに反するとされた者は断罪され、抹殺されるということが起こる。それは「聖書」の権威を傘に、自らを絶対化・正当化する暴力である。”
“イエスの事蹟を人々が書き記し、編纂してきた聖書は、“聖典”として絶対視するものではない。歴史的・批判的立場から聖書と向きあうことこそ、信仰者にも無信仰者にも望まれる。福音書の新しい読み方。”
“特定の教派によらず,自主独立で読む.聖書学者が,自身の経験と思索をもとに提案する「わかる読み方」.”




